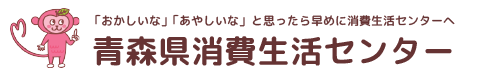テルミちゃんの知って得する知恵袋「害虫・害獣駆除のトラブルに注意」
インターネット広告などで「格安」「〇〇円~」「すぐ駆けつける」とうたう業者にハチの巣の駆除を依頼したところ、予想外の高額料金を請求されたという相談が消費生活センターに寄せられています。
こんな相談がありました。一人暮らしの高齢女性宅の軒下に、キイロスズメバチの巣が見つかりました。困った女性が親戚に相談すると、その親戚がインターネットで、「ハチの巣の駆除3千円~」という広告を見つけ、業者に問い合わせました。業者から、「料金は巣を見てみないとわからない」と言われましたが、「3千円~」の広告が印象に残っていて、そんなに高額にはならないだろうと思い、その業者に来てもらうことにしました。数日後、防護服を着た作業員が一人でやってきて巣を確認し、「料金は5万円かかる」と言いましたが、そんなものかと思い、そのまま作業をお願いしました。ほどなく作業が終了し、業者から渡された契約書兼請求書を見ると、税込み17万円と記載されていました。作業前には5万円と言われていたのに、作業後17万円という高額な請求をされ納得できないというものです。
この事例では、業者が訪問してから料金が告げられ、駆除を依頼することになったため、訪問販売とみなし、クーリング・オフが可能であることを説明しました。しかし、相談者はクーリング・オフはしないこととし、業者と交渉した結果、料金を減額してもらうことで終了しました。
くらしのレスキューサービスと称して、害虫・害獣の駆除ばかりではなく、水回りの修理、ロードサービスなど「〇〇円~」と低額な最低料金を目立つように広告し、いざ作業を依頼すると驚くほど高額な料金を請求されるという相談が後を絶ちません。極端に安い価格で「すぐに駆けつける」という広告には注意しましょう。緊急の対応が必要な場合だからこそ、このような広告の業者に頼りたくなりますが、平時から信頼できる業者を見つけて、いざという時に備えておくと安心です。頼れる業者がいない場合でも、慌てず複数の業者から見積もりをとって比較検討し、強引に契約を勧めるような業者とは契約しないようにしましょう。
困った時は、早めに消費者ホットライン188にご相談ください。
テルミちゃんの知って得する知恵袋「子どものオンラインゲーム」
近年、家庭へのスマートフォンの普及が急速に進んだ結果、子どもが利用する機会も増えています。子どもがスマホのゲームに夢中になっているうちは家事や仕事がはかどるため、スマホを育児に欠かせないアイテムとしている保護者も多いことでしょう。
しかし、今、子どものスマートフォン課金トラブルが増加しています。うちの子どもは無料のゲームしかしないので大丈夫などと過信せず、注意が必要です。
子どものオンラインゲームにまつわるこんな相談がありました。ある日、クレジットカード会社から「カードで16万円が使用された。不正利用の可能性があるためカードの利用停止する」と連絡がありました。不審に思い、カード会社やゲームの運営会社に問い合わせると、10歳の子どもがオンラインゲームで課金をしたり、動画投稿サイトで投げ銭をした料金だったことが判明しました。子ども用に購入したスマホは、保護者のIDでログインした状態のまま子どもに渡していました。課金制限するつもりでしたが、うまく設定できず、何も対策を講じていませんでした。
10歳の子どもが課金したのだから、民法で定められた未成年者取消権によって契約を取り消せばいいと思われた方もいると思います。しかし、この事案では、実際にスマホを操作したのが子どもでも、保護者のIDで課金が行われており、保護者自身が契約したようにみえるため、未成年者取消権は認められませんでした。また、全額返金を求めて、保護者から課金に至った経緯をカード会社に提出しましたが、課金の都度、クレジットカードの利用通知が届いているのに気づかないのは考えにくいなどの理由から、保護者の管理責任が問われることになり、結局、約7割の返金で和解が成立しました。
子どものデジタルスキルは、保護者の想像を超えるスピードで進化します。保護者のスマホにクレジットカード情報が残っていると、クレジット払いの意味も知らず、際限なく課金できる打ち出の小づちを得たかのようにカード決済を続けてしまうことでしょう。子どもにスマホを使わせる場合は、クレジットカード情報は削除し、保護者のアカウントからログアウトした状態にしてから渡しましょう。子ども専用スマホの場合は、ペアレンタルコントロール機能を設定し、保護者が使用状況を把握できるようにしておきましょう。
また、子どもと話し合い、オンラインゲームで遊ぶ際のルールを決めておくことも大切です。
困った時は、早めに消費者ホットライン188にご相談ください。
テルミちゃんの知って得する知恵袋「5月は消費者月間です」
消費者保護基本法(消費者基本法の前身)が1968年5月に施行されてから20周年を迎えたことを機に、1988年から毎年5月が消費者月間とされました。今年の消費者月間統一テーマは、「デジタル時代に求められる消費者力とは」です。
デジタル化やAI等の技術の進展し生活が便利になる一方で、リスクも多様化しています。そうしたデジタル時代において、わたしたちが安全・安心かつ豊かな消費生活を送るために、今、求められる「消費者力」とはどのようなものでしょうか。
2023年1月から12月までの県内の特殊詐欺の認知件数は、過去最悪の97件、被害額は3億円を超えました。手口としては、インターネット上で行われる詐欺が急増し、電話によるオレオレ詐欺やはがきによる架空料金請求詐欺などのアナログタイプは減少しています。実際、2023年度に県の消費生活センターに寄せられた相談のうち、約4分の1がインターネット上の契約に関わる相談でした。
このように増加するインターネット詐欺の中で、特にフィッシング詐欺(大手通信会社を名乗るメールやSMSに記載されたURLから偽サイトに誘導し、誘導先のサイトでIDやパスワードなど個人情報を入力させて、その情報を盗み取る手口)の被害が後を絶ちません。
また、投資詐欺(SNSで知り合い、一定の時間をかけて親しくなったところで投資話を持ち掛けて送金させ、あたかも利益が上がっているように巧妙なアプリを仕込んでお金を騙しとる手口)も昨年から深刻さを増しています。
このような被害に遭わないためには、デジタルサービスの仕組みやそのリスクを理解して、情報に対する批判的思考力や適切に情報を収集・発信する力を常に更新していくこと、そして「気づく力、断る力、相談する力」を高めていくことがとても重要です。
デジタルと聞いただけで苦手意識を持つ方もいるかもしれません。得意な人もそうでない人も等しくデジタル化のメリットを最大限享受し、安全・安心な消費生活を送るため、デジタル時代を生き抜く消費者力を身に付けましょう。その過程で、思わぬトラブルに巻き込まれそうになった時は、早めに消費者ホットライン188にご相談ください。
テルミちゃんの知って得する知恵袋「借金で困ったら、早めに相談しましょう」
人生で最も高い買い物は「家」だと考える方は多いと思います。戸建住宅やマンションを現金一括払いで購入する人もいますが、大多数は将来の生活設計を描きながら住宅ローンを組むことでしょう。ところが最近、住宅購入後に、当初の生活設計が狂い、想定外の借入れによって生活が圧迫され精神的に追い詰められるケースが増えています。
ある40代の男性は、住宅ローンや自動車ローンを抱えた状態で、生活費や子供の学費などのために借入れを重ね、借入金返済のために新たな借入れをするという悪循環に陥ってしまい、気がつくと住宅ローン以外の負債が1,500万円に膨らんでいました。毎月の返済額の合計が給料の額を超えてしまい、とうとう返済することができなくなった男性は追い詰められ、消費生活センターに相談しました。
消費生活センターは、男性を弁護士につなぎ、その結果、男性は住宅を手放すことなく債務整理ができる「個人再生」の方法で手続きを進めることになりました。
複数の業者から借金をしていて、返済が困難になっている状態のことを多重債務といいます。多重債務の状態になると、いくつもの返済期限に追われ、経済的にも精神的にも非常に苦しい生活になってしまいます。多重債務に陥った場合は、裁判所を介して債権者と返済計画を話し合う「特定調停」、裁判所を介さず、弁護士等の専門家に委任して債権者と返済方法を話し合う「任意整理」、裁判所に申し立てて住宅を残しながら借金を減額できる「個人再生」、裁判所に申し立てて現金、住宅などの資産を売却し、債権者に配分することを条件に、すべての債務を免責してもらう「自己破産」の4つの債務整理方法があります。相談することで、悩みを他者と共有することができるほか、専門家から助言を得ることで早期の解決が図られることが期待できます。消費生活センターだけではなく、青森県弁護士会、消費者信用生活協同組合、青森財務事務所など複数の窓口がありますので気兼ねなく相談してください。
「もっと早く相談すれば良かった」と後悔しないよう、一人で悩まず一日も早く消費者ホットライン188に相談してください。
テルミちゃんの知って得する知恵袋「クリーニングトラブル」
日差しにぬくもりが増してくると、重いコートやジャケットから軽いコートに衣替えをする時期になります。数カ月間お世話になった冬物は、クリーニングでキレイにして保管し、次の冬に備える方も多いと思います。家庭用の洗濯機の機能が進化し、デリケートな衣類に配慮した洗剤等も増え、衣類をクリーニングに出す機会は少なくなったかもしれませんが、大切な衣類については、やはりプロの手に委ねたいと考える方も多いのではないでしょうか。
60代の男性からこんな相談がありました。1年ほど前、14万円で購入した礼服を1度着用し、クリーニングに出しました。最近になって葬儀に参列するために、礼服を着用しようとビニールから出してみると、左袖の一部が縮んだようになり、右袖にも少し擦れたような跡がついていることに気付きました。受取り時に確認しなかった自分にも落ち度があると思うが、店の過失が大きいので全額賠償してもらいたいという内容です。
しかし、クリーニング店は既に廃業しており賠償を求める先はもうありません。また、クリーニング事故賠償基準では、消費者が洗濯物を受取ってから6カ月、または、クリーニング業者が洗濯物を受け取った日から1年を経過した時は、賠償額の支払いを免れることになっています。仮にクリーニング業者が営業を続けていたとしても、この事例では賠償してもらうことはできないでしょう。
クリーニングトラブルでは、「シミ」「変色」「伸縮」「紛失」などのトラブルが起こることがあります。これらのトラブルは、単にクリーニング業者側の過失だけではなく、衣類製造者や消費者側の問題で発生する場合もあります。例えば、洗濯物のビニールカバーを外さずに保管したために、衣類が変色することもあります。
クリーニングトラブルは複数の要素が重なって発生することもあるため、原因の特定が難しく、時間が経つとより原因究明が困難になります。そのため、洗濯物の受け渡し(出す時、受け取る時)には、衣類の状態を双方でよく確認することが大切です。また、クリーニング事故の損害賠償金が支払われる場合でも、購入時からの経過年数や衣類の状態が勘案されるため購入時の金額が戻るわけではありません。
困った時は、早めに消費者ホットライン188に相談してください。
テルミちゃんの知って得する知恵袋「投資に関するトラブル」
日本銀行の2023年「資金循環の日米欧比較」によると、日本では家計金融資産のうち、現金・預金が占める割合は50%を超えている一方、株式等・投資信託の割合は約15%と米国の約51%に比較するとかなり低い状況にあります。そこで国は、将来にわたって個人の金融資産を増やしていくために、今年1月から始まった新しいNISA(少額投資非課税制度)など、貯蓄から投資へシフトさせる施策を進めています。しかし、「投資」の気運が高まる一方で、投資に関するトラブルは増加傾向にあり、被害の深刻さも増しています。
県内に住む60代の男性は会員制SNSで投資をしている人と知り合い、その人物から紹介されてFX取引を始めました。最初に20万円を指定された口座に振り込むと、アプリ上でもうけが出たことが確認できたため、信用してさらに80万円を振り込みました。振込先の銀行口座は、2回とも投資事業者とは異なる個人の名義でした。これ以上、投資できるお金がないことを事業者に伝えると、お金を融資する内容の契約書が送付されましたが、届いた契約書に押された社印に不信感を持ったため娘に相談すると、「詐欺ではないか」と言われました。振り込んだお金を取り戻そうと振込先の銀行に問合せたところ、振り込め詐欺疑いで口座凍結になっていることがわかりました。
投資詐欺でよく用いられる手口として、最初は少額を投資させ、「もうかる」という成功体験をさせることがあります。この投資話は本物だと信用させ、安心して追加投資を重ねるよう仕向けます。自分の投資金の利益の変動を随時確認できるようにアプリをインストールさせ、チャート上は日々利益が膨らんでいく様子を見せられると、それが偽の情報だと気づきにくくなります。
投資にリスクはつきものです。「簡単に稼げる」「もうかる」ことを強調する広告は安易に信用してはいけません。また、投資は余裕資金で行いましょう。借金をして投資をしても、貸付利息以上のもうけを得られる保証はありません。借金を勧められたら詐欺を疑いましょう。
少しでも不安があれば、早めに消費者ホットライン188にご相談ください。
テルミちゃんの知って得する知恵袋「海産物の強引な電話勧誘にご用心!」
福島第一原子力発電所のALPS処理水の放出に対して強い懸念を示していた中国が、日本からの海産物の輸入を一方的に停止したことは、日本の水産業へ大きな打撃となり、今でもその余波が続いているのは事実です。それに便乗して同情を誘い、不当な利益を得ようとする者がいます。
ある日、見知らぬ業者からスマートフォンに電話があり、海産物セットの購入を勧められました。「福島第一原子力発電所の処理水の放出問題のせいで、ホタテや海産物が余ってたいへんだ」と話していました。最初は1万5千円と言っていましたが、購入を渋っているうち1万2千円に値引きされましたが断りました。しかし、断っても断っても執拗に勧誘を続けるため、業者の窮状を救うことになるのであれば協力をしようと思い直し、購入することにしました。しかし、電話を切ったのちによく考えると信用できる業者なのかも疑わしいし、そもそも欲しくて申し込んだわけではないので、やはり断ろうと業者にキャンセルの電話をしましたが、呼出し音が鳴るだけで電話に出ません。
以前から海産物の強引な電話勧誘に関するトラブルの相談は高齢者を中心に多数寄せられています。このような勧誘をする業者は、その時々の情勢に巧みに便乗し、慈愛の心を持つ人々の優しさにつけ込んで価格に見合わない貧相な海産物を詰め合わせて送っています。中には、はっきりと「買いません」と宣言した人宛てに勝手に代引き配達で送りつけることもあります。
電話で勧誘されて商品を購入する場合は、契約書を受取った日を含めて8日間はクーリング・オフが可能です。業者は、電話で勧誘をする前に、社名を名乗り海産物の販売をする目的の電話であることを告げなければなりません。また、買うつもりはないとはっきり告げている人に、同じ商品の勧誘を続けることも法律に抵触する行為です。一方的に送りつけられた商品を返品する必要もありません。強引な勧誘電話は、きっぱりと断ったうえで、すぐに切りましょう。相手のペースに巻き込まれてしまう前に毅然と対処することが大切です。電話を切ることは相手に対して失礼ではありません。
少しでも不安があれば、早めに消費者ホットライン188にご相談ください。
テルミちゃんの知って得する知恵袋「葬儀に関するトラブル」
人はいつか必ずお別れの時がやってきます。親族は、悲しみにくれる間もなく別れの儀式の手配に追われるのが現実です。葬儀は、結婚式のように予め日程が決まっていて十分な準備を経て執り行うものではなく、突然始まり短時間のうちにあらゆることを決定しなければなりません。失意の中で不慣れな儀式の契約をして、トラブルに発展するケースも決して少なくはありません。
病気療養中の義父が余命宣告を受けたため、万が一に備えようと葬儀社の見学をしました。その際、互助会に入会すると葬儀費用は40万円の値引きが適用され、百万円程度の支払いで済むと説明があったため、互助会に入会することにしました。数ヶ月後、義父が亡くなり、夫が葬儀社に連絡し、当日の深夜にもうろうとした意識の中で葬儀の打合せをしました。しかし、家族葬や一日葬などの葬儀のスタイルに関する説明や選択の余地はないままどんどん話が進み、最終見積額として190万円が提示されました。百万円程度で済むという当初の説明と違うと抗議すると、「喪主にはサインをもらっているから、変更はできません」と聞き入れてはくれませんでした。
せっかく、葬儀に備えて事前に業者選びをしたはずが、最終的に消費者の意図しない契約になりました。消費者は慣れない葬儀の契約内容をよく理解できず、一方の事業者側は、「慣れ」からか説明を尽くしたつもりになってしまい説明が不足していた可能性もあります。葬儀社との打合せの際は、説明の聞き漏らしや確認のし忘れを防ぐためにも、冷静に判断できる第三者に同席してもらいましょう。
葬儀費用は、参列者の人数によって増減する「変動費」と言われる項目(人件費、料理、香典返し)が大きな割合を占めています。参列者数を少なく見積もると、見積額と実際の請求額が大きく異なってしまう場合もあります。安価な価格設定になっている場合は、その料金に含まれる項目と含まれない項目の料金体系はどうなっているのかしっかり確認する必要があります。現代では葬儀の話は決してタブーではありませんので、日頃から家族で話し合いをしたり、信頼できる葬儀社の情報収集をするなどしていざという時に備えておきましょう。
少しでも不安があれば、早めに消費者ホットライン188にご相談ください。
テルミちゃんの知って得する知恵袋「火災保険申請代行のトラブル」
万が一の災害に備えて財産を守るために、多くの人が火災保険に加入しています。保険の種類によって補償される範囲は異なりますので、自分が加入している保険がどんな時に支払われるのか日頃から知っておくことはとても大切なことです。仮によくわからないとしても、保険会社や代理店などに確認することで、次のようなトラブルに巻き込まれずにすむかもしれません。
高齢の母親が家の外にいたところ、「巡回して古い家にお住まいの方に声をかけています。屋根が雪で壊れていませんか。保険金を使って直せますよ」と声をかけられました。業者は、保険会社に損害申請をするサポートをしてくれると言い、書類を見ながら説明を受けるうちに、いつの間にか、契約書に署名をしてしまいました。業者が帰った後で、知り合いの工務店に相談すると、「調査するだけで5万円、保険金が支払われたら45%の報酬を支払うよう契約書に書かれている。怪しいのですぐにキャンセルした方がいい」と助言され、すぐに業者に連絡をしましたが「お金がもらえる話なのに何が不服なのか」と、なかなかキャンセルに応じてくれませんでした。
本当に雪害が原因で壊れたのであれば、保険金の請求をすることも可能ですが、このような勧誘をする業者の最大の問題点は、保険金の支払い対象外である経年劣化や自然損耗が原因で壊れたものであるにも関わらず、災害で壊れたと偽って保険金を請求するよう促すことです。これは「詐欺」に該当し、消費者も詐欺に加担することになります。また業者は、支払われた保険金の30~50%もの高額な報酬を請求します。これでは、肝心の住宅修理などできるはずがありません。この矛盾に気づいて解約しようとすると、同じように高額な違約金を請求されます。
火災保険の申請は、加入者自身で行えば、お金をかけることなく保険金を受け取ることができます。火災保険の申請をサポートするという業者とは関わらないようにしましょう。
電話勧誘や訪問販売で契約した場合は、8日間以内であればクーリング・オフが可能です。少しでも不安があれば、早めに消費者ホットライン188にご相談ください。
テルミちゃんの知って得する知恵袋「エステティックサービスのトラブル」
新型コロナ感染防止対策のマスク着用の考え方の見直しにより、人前でマスクを外す機会が増えたので、お肌の状態を気にする方も多いのではないでしょうか。さらに最近では、男性の間でもツルツル、スベスベの肌に憧れて、エステサロンを利用する方も多くなっているようです。
県内に住む20代の男性は、そんなエステサロンを利用する1人でした。サロンに通い始めて半年余りが過ぎた頃、他県への転勤の内示がありました。サロンに通うことができなくなるので、中途解約を申し出ました。すると、サロンの担当者から「キャンペーン中の契約なので、現金での返金は難しい。残金はサービスか店の商品で返す」と言われました。ヒゲ脱毛コースなど計7万円を一括で支払っており、まだコースの半分程度しか施術を受けていないので、残りは現金で返金してもらうことはできないのかと消費生活センターに相談がありました。
契約約款を確認したところ、法律に沿った中途解約の計算式が掲載されており、キャンペーン中の契約だから現金での返金が不可であるという記述はどこにもありませんでした。このため、現金で返金すべきだという消費生活センターの見解を伝えたうえで、再び相談者が交渉をしたところ、すぐに現金で3万円が返金され、解決することができました。
エステティックサービスは、特定商取引法により、一定の条件のもと「特定継続的役務提供」としてさまざまな規制が設けられています。実際に施術を受けてみなければ良し悪しの判断は難しく、施術期間が長期に渡ることもあります。「無料体験」や「お試し」の言葉にひかれ、1回限りの施術に出向いたつもりが、施術台に乗せられたまま長期コースの契約を執拗に勧められ、断り切れずに高額な契約をしてしまうという事例もあります。長期コースの契約をする場合は、中途解約や返金の条件をよく確認しましょう。特に「通い放題」のコースの場合、契約の仕組みが複雑で解約時のトラブルが多くなっていますので注意が必要です。断り切れずに契約をしてしまったら、8日以内であればクーリング・オフができます。本当に必要な契約か冷静に考えてみましょう。
少しでも不安があれば、早めに消費者ホットライン188にご相談ください。