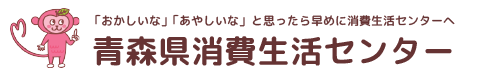若者向け情報に動画「若者の脱毛エステなどのトラブルに注意!(他3本)」をアップしました
ちょっと待って!テルミちゃん第90回「借金で困ったら早めに相談しましょう」をアップしました
ちょっと待って!テルミちゃん第89回「キャッシュレス決済は安全に利用しましょう」をアップしました
ちょっと待って!テルミちゃん第84回「海産物の強引な電話勧誘に注意」をアップしました
ちょっと待って!テルミちゃん第83回「投資のトラブルに注意」をアップしました
【相談】海産物の強引な電話勧誘にご用心!
【事例】
昨日、見知らぬ業者からスマートフォンに電話があり、海産物のセットの購入を勧められた。「福島第一原子力発電所の処理水の放出問題のせいで、ホタテや海産物が余ってたいへんだ」と話していた。最初は、15,000円と言っていたが、購入を渋っているうちに、12,000円に値引きすると言われたが断った。断り続けていたがあまりにもしつこく勧誘されたため、根負けして承諾してしまった。商品は1週間後に届く予定だが、欲しくて申し込んだわけではないので、やはり断ろうと業者にキャンセルの電話をしたが、呼出し音が鳴るだけで電話に出ない。解約することはできないか。
( 契約当事者:50代 女性 )
<センターの対応>
相談者から聞き取った連絡先に電話をしてみましたが、相談者の言う通り、呼出し音は鳴るものの誰も出ず、折り返しの連絡もありませんでした。相談者の着信履歴を見てもらうと、携帯電話番号から勧誘の電話が入っていたため、海産物の契約をクーリング・オフすること、この件については消費生活センターに相談していることをショートメッセージサービスで送信するよう助言しました。
後日、代引き配達で荷物が届きましたが、送付状に書かれた住所・業者名を画像に残し、受取りを拒否しました。その上で、改めてクーリング・オフのハガキを業者宛てに送付して終了したと相談者から報告がありました。
<アドバイス>
海産物の強引な電話勧誘に関する相談が依然として多くなっています。一度も取引をしたことがないのに、「以前購入してもらった方に電話をしています」と、これまでも付き合いのあった業者のように親しげに迫ったり、新型コロナウイルスの感染が拡大し、海産物等の消費量が激減していることが報道されると、「新型コロナウイルスの影響で商品が売れずに困っており廃業も考えている。助けて欲しい」と情に訴えて契約させようとします。最近も、事例のように福島第一原子力発電所の処理水放出による、中国の海産物禁輸措置の影響に便乗して、人の善意につけ込むようなトークで勧誘をしていると思われます。
このように販売された海産物をいざ受け取ってみると、貧相な加工品ばかりでとても価格に見合うような商品ではなかったり、きっぱり断ったにもかかわらず代引配達で商品を送りつけるなど問題点が多数見受けられます。
はっきりと業者名を名乗らない、必要以上に情に訴える、強引な勧誘を続ける電話は、相手のペースに巻き込まれる前にきっぱり断り、電話を切りましょう。このような勧誘の電話を切ることは相手に失礼などと配慮する必要はありません。
また、業者からの電話勧誘で契約をした場合は、契約書面を交付された日から数えて8日以内であれば、クーリング・オフが可能です。クーリング・オフは書面またはメール等でも可能です。
少しでも怪しいな、困ったなと思ったら、消費者ホットライン☎188に相談してください。
ちょっと待って!テルミちゃん第78回「エステのトラブルに注意!」をアップしました
【相談】保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意
【事例】
「火災保険を使って家の修理をしないか」という電話があり、自己負担無しで家の修理ができるのであればと思い承諾した。翌日業者が来訪し、雨どいの写真を撮り、火災保険の申請サポートと雨どいの修繕工事の契約をした。しかし、契約書をよく見ると「万が一、保険金が支払われたにも関わらず、弊社の指定工務店にて工事されない又は保険金のお支払いをしてたいただけない場合が生じたときには、誠に不本意ながら、現地調査費用と申請書作成費用として、受取保険金の50%をお支払いいただきます」と記載があった。保険金の範囲内で工事をしてくれるなら問題はないと思うが、家族が心配してネットで調べたら、火災保険の申請代行をするという業者に関するトラブルが多いことを知り、クーリング・オフをすることを勧められた。クーリング・オフの方法を教えて欲しい。
( 契約当事者:60代 男性 )
<センターの対応>
相談者は既にクーリング・オフのハガキを準備しており、内容に問題はなかったため、そのまま書留で発送しました。念のため相談を受け付けた消費生活センターから業者に連絡し、クーリング・オフする旨伝えたところ、了承されました。
<アドバイス>
火災保険を使って住宅の修理をしないかと持ちかける業者に関する相談が令和3年度以降県内でも寄せられるようになりました。しかし、令和5年度に入って相談が急増し、7月までで、前年同期比の13倍を超える相談となっています。
これまでは。保険金の請求を代行するとうたったインターネット広告を見て、自ら申込みをする事例が多く見受けられましたが、最近では電話勧誘販売もしくは訪問販売が圧倒的に多くなっており、契約当事者の年代もほとんどが60代以上となっています。
この手口の最大の問題点は、風雪水災等の突発的な出来事により生じた損傷ではない、経年劣化による損傷を災害と偽って保険金請求をするよう促す点です。このような虚偽の申請は「詐欺」に該当する可能性があります。
また、次の問題は、業者に支払う高額な報酬です。支払われた保険金の35~40%を報酬として請求します。保険会社が支払う保険金はあくまで修理費用分ですから、報酬を差し引いた保険金額では修理をすることはできません。そもそも、保険金の請求は契約者自身が保険会社に請求すべきものですし、サポートが必要であれば、担当の保険代理店にお願いすればお金がかかることはありませんので、高額な報酬の支払いは必要ありません。
風雪水災等で住宅の損傷がわかったら、加入している保険会社に自ら問合せをし、「火災保険を使って住宅を修理しないか」と勧誘する業者とは関わらないようにしましょう。
少しでもおかしいと思ったら、お早めに消費者ホットライン☎188(いやや)に相談をお願いします。